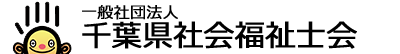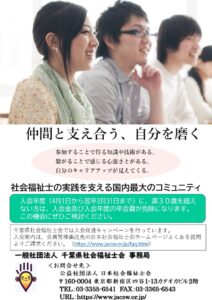今後の令和6年能登半島地震被災地への支援
千葉県社会福祉士会では、令和6年能登半島地震被災地に対する支援活動として、昨年4月以降石川県社会福祉士会が取り組む「被災者見守り・相談支援事業」に対して活動希望会員を派遣してきました。会員の皆様のご協力により、本年3月末での実績として延べ17人、同57日の派遣状況となっています。
金沢市内のみなし仮設住宅に移り住んでいる被災者の方々にとって、暖かくも力強い支援活動の一端を担い得ているものと、改めて会員の皆様のご協力に感謝申し上げます。
さて、今後の支援活動ですが、災害支援本部での討議により、『会員派遣は継続するが、派遣会員に対する本会からの活動補助金の支給は6月30日活動分をもって終了する』と方針を決定いたしました。
その理由は、現地における派遣者必要数がピーク時の12人から4人に減少している、地元の方々が主体となった生活復興・被災者支援が動き出しているなど、全国からの集中的な支援が求められる急性期の状況を脱しつつあると判断したからです。
なお、7月以降も金沢市での支援事業は引き続き実施されますので、本会においても派遣を希望される会員に対しては、説明会の実施、受け入れ先との連絡調整などのサポートは継続していきます。
災害対策における他の取り組みとして、災害対策委員会においては、これまでの支援活動の体験を会全体で共有するとともに、国における新しい災害対策の動向を学ぶために、「能登被災地支援活動報告会・研修会」を7月12日に開催する予定です。開催の折には多くの方々にご参加いただけるよう報告会・研修会PTでの企画検討を進めています。
最後になりますが、千葉県においても、豪雨や台風だけでなく、南海トラフ地震による被災、更には半島地域特有の支援活動の困難さ等が憂慮されています。これからも、本会の被災地支援活動に対して会員の皆様のご理解とご協力をいただけますよう、お願い申し上げます。
令和7年4月21日
千葉県社会福祉士会
会長・災害支援本部長
澁澤 茂
(お問合せ:災害対策委員会)
cswchiba3saigai@gmail.com
災害支援本部からのお知らせ(災害時情報集約掲示板)
★石川県への派遣を希望される方(被災地支援活動協力員)を募集します(令和7年4月21日掲出)
・募集期間:令和6年5月より 当分の間
・派遣時期:登録完了後に石川県社会福祉士会が提示する活動日程。連続3日が基本。
・活動場所:金沢市内及び隣接市町(今後拡大の見込み)
・宿泊施設:活動拠点から徒歩5分程度の場所に確保(無料、ホテル等ではない)
・活動補助:1日2万円(石川県士会から15,000円、千葉県士会から【6月30日活動分まで】5,000円)
*交通費・食事代相当額を含む。
・活動保険:「社協役員・職員の業務中の傷害保険」に加入(自己負担なし)
・エントリー:下記応募フォーム(千葉県社会福祉士会宛て)に記入して下さい。
https://forms.gle/g44yyZ8hgBWSo4qk6
*QRコードからも応募フォームにアクセスできます。
応募フォームQRコード
・派遣対象者:被災地支援活動協力員登録者
未登録の方は、下記から新規登録してください。
https://www.cswchiba.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/08/cd42c739f1d0dd61eae319f228d4a77f-1.pdf
◎会員派遣の状況(令和7年3月31日までの累計)
・延べ派遣会員数:17人
・延べ活動日数:57日
◎次回の説明会・派遣者選考の開催
現在のところ予定はありません。
派遣希望者は、下記応募フォーム(千葉県社会福祉士会宛て)に記入して下さい。
https://forms.gle/g44yyZ8hgBWSo4qk6
*支援活動に関する不明点等は災害対策委員会にご相談ください。
cswchiba3saigai@gmail.com
<関連情報>
・石川県社会福祉士会ホームページ https://csw-ishikawa.com/
・FACEBOOKグループ「災害ソーシャルワーカー交流空間」
https://www.facebook.com/groups/182381734950606
★会員派遣により被災地支援活動をした方は活動補助金を申請してください(6月30日分まで)
・対象:会員派遣により石川県社会福祉士会の「被災者見守り・相談支援事業」で活動した方
・金額:1日5,000円(6月30日活動分まで)
・活動の範囲:支援活動に従事した日のみ(往復の移動日は含まない)
該当する方は、下記の申請書フォームから手続をして下さい。必要な手続等は、申請書フォームに記載しています。
⇒(会からの派遣者用)令和6年能登半島地震に関する被災地支援活動報告書兼活動補助金支給申請書
https://forms.gle/drEc2orpj3js2bfz5
◆被災地支援活動協力員の登録など本会の被災地支援活動
以下からご覧ください。
https://www.cswchiba.com/?page_id=13915
「こどもがみらいへの選択肢を増やせるために」の声明文について
千葉県社会福祉士会は、令和6年8月15日に千葉県知事、千葉県教育長に「こどもが未来への選択肢を増やせるために」と表した声明文を届けました。
きっかけは、昨年度頃から複数の方からのご相談をいただいたことです。普通高校への入学を希望し、定員に満たない高校を受験したが合格できなかったとのことでした。当事者は重度の障害をおもちの方で、何年も受験を続けているが合格できず、浪人生活を続けていらっしゃいました。
このことについて、同様の相談を受けている、千葉県弁護士会と一緒に現状の理解に努めました。会員には、広報誌「点と線」に声明文案を同封して意見を募りました。学校関係者等にも意見を伺いました。有志による話し合いを重ね臨時の理事会も開催しました。
立場によって様々な意見があることを伺いました。定員内不合格について、やむを得ないのではないかという意見も聞きました。
それでも私たちは、「誰もが、自分の学ぶところは自分で選べるようにできるべきである」という自己決定の原則を重視すべきと考え、声明文を発出しました。子どもには自由に意見を表明する権利があることを踏まえて、その意思形成のために体験の付与と機会を保障することが重要であると考えており、その支援のために尽力したいと思っています。
【定員内不合格とは】
公立高校入学者選抜試験(以下、公立高校入試)を受験した生徒数が募集定員に満たなくても不合格となる、いわゆる「定員内不合格」が国会においても議論となっている。公立高校入試における合格者の決定は、学校教育法の施行規則により各高校の校長が許可することになっているが、定員内不合格者については都道府県ごとに対応が分かれている。
公立高校入試の方針については、戦後10年あまりは基本的には「志望者全員入学」で「定員超過の場合は学力検査による選抜を認める」となっており、1950年には「募集人数から定員割れした場合は全員入学を許可する」という通知も発出された。しかし、1963年、第1次ベビーブームの子どもたちが高校入学者年齢になったことで、「入学者を選抜する方針(適格者主義)」に変更された。その後、1984年に高校の進学率が94%に達したこともあり、文科省は「一律に適格者主義を前提としなくてよい」旨の通知を発出し、方針を変更したことで、複数の都府県では「定員内不合格」は解消された。一方で、定員内不合格を一律に否定するわけではない旨の国会答弁もなされており、具体的な対応は現場の判断に委ねられているのが現状である。なお、文科省としては「総合的判断という説明では説明責任を果たしたことにはならず」、「定員内不合格を出さないよう取り扱っている例を含め、他の教育委員会における入学者選抜の実施方法等を参照するなどしていただくとともに、合理的な説明となっているかについて改めて御検討いただくようお願いします。」との通知を令和6年6月に発出している。
千葉県内の公立高校入試の対応は、様々な理由があるにせよ、特に重度の障害がある入学志望者については、定員内不合格を認めるものとなっているのが実態である。
令和6年8月15日
一般社団法人千葉県社会福祉士会
会長 澁澤 茂
事務局移転のお知らせ
当会事務局は2023年(令和5)4月1日開設の千葉県社会福祉センターへ移転しています。
千葉県社会福祉センターへの来訪可能です。なお駐車場が限られておりますので公共交通機関をご利用ください。
新住所:〒260-0026 千葉県千葉市中央区千葉港4-5 千葉県社会福祉センター5階
TEL:043-238-2866 FAX:043-238-2867
※電話番号、FAX番号等変更ありません。
一般社団法人 千葉県社会福祉士会事務局
入会促進キャンペーン中!
入会年度(4月1日から翌年3月31日まで)に、満30歳を超えない方は、入会金及び入会年度の年会費が免除になります。
この機会にぜひご検討ください!
入会案内は、会員管理委託先の日本社会福祉士会ホームページよりご請求ください。(下記より日本社会福祉士会ホームページよくある質問ページに移動できます)日本社会福祉士会入会手続き(日本社会福祉士会ホームページへ移動します)
広報誌「点と線」をメールで受け取りませんか?
会員の皆様へ、下記からお申込みください。
一般社団法人千葉県社会福祉士会の想い
地域共生社会の実現に向けた方向性は、20世紀末に示された「社会福祉基礎構造改革」以来、戦後2度目の社会保障制度の大きな転換期です。福祉サービスを拡充することだけでは保てなくなった社会を「共助」に重点をおいて再構築しようとするものです。縦割りの福祉が分野統合され、福祉と他分野の垣根が見えなくなっていき、さらには地域の中に混在化されていく。そんな方向性が描かれています。
その中で、人間の福利の増進を目指して、社会の変革を進めるソーシャルワーカーの役割は重要です。当事者が抱える課題について適切な社会資源とつなげること、あるいはそれを創造して社会の中に配置していくことが求められるからです。
千葉県社会福祉士会は発足以来、日常生活や介護のことなど、生活の困りごとが起きたときに「福祉の道案内役」として県民の皆様に役立ててもらえるよう、日々活動しています。
社会福祉士はソーシャルワークの定義に沿った活動が出来ているのか研鑽します。それを皆で共有する機会を持ちたいと思います。司法や医療、教育等の他分野との協働をさらに進め、会員内外の方の想いを組み入れた活動が出来るように努めます。